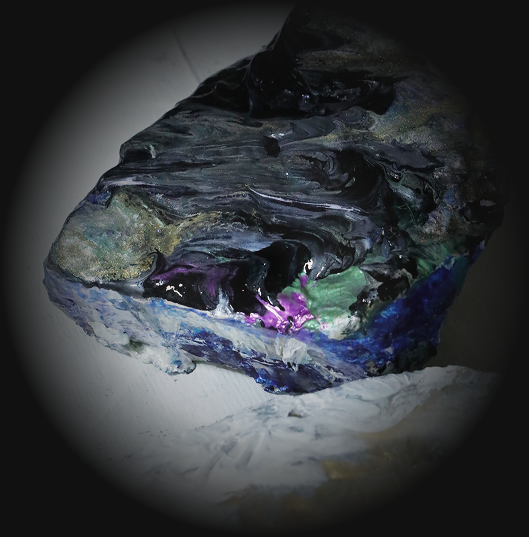倉貫徹について
1948年に大阪に生まれました。幼少期から宝石や鉱石など美的な要素に親しんで育ち、自然と芸術の世界へと傾倒していきました。その後、約50年にわたり現代美術の分野で活動を続けています。
1970年代初頭には、前衛芸術運動である「具体美術協会」に関わり、現代美術の新しい潮流に積極的に参加しました。1971年には今井祝雄氏とともに自宅の屋上で「Roof Show」を開催し、翌1972年には今井祝雄氏、村岡三郎氏とともに大阪・道頓堀で「This Accidental Co-action as an Incident」と題したストリート・パフォーマンスを行いました。心臓の鼓動音を拡声器で街に響かせるなど、現実と芸術の境界を揺さぶる実験的な表現に挑みました。
1970年代後半からは活動の場をさらに広げ、大阪・信濃橋画廊を中心に数多くの展覧会を開催しました。1980年代にはアメリカやベルギーなど海外にも活動を展開し、1990年と1991年にはニューヨークのPamela Auchincloss Galleryにて個展を開催しています。これまでに国内外でおよそ80回に及ぶ個展やグループ展に参加し、その歩みを重ねてきました。